
就労移行支援中の生活費はどうする? 収入源・支援制度・相談先を解説
公開日:2025.07.05
更新日:2025.07.04
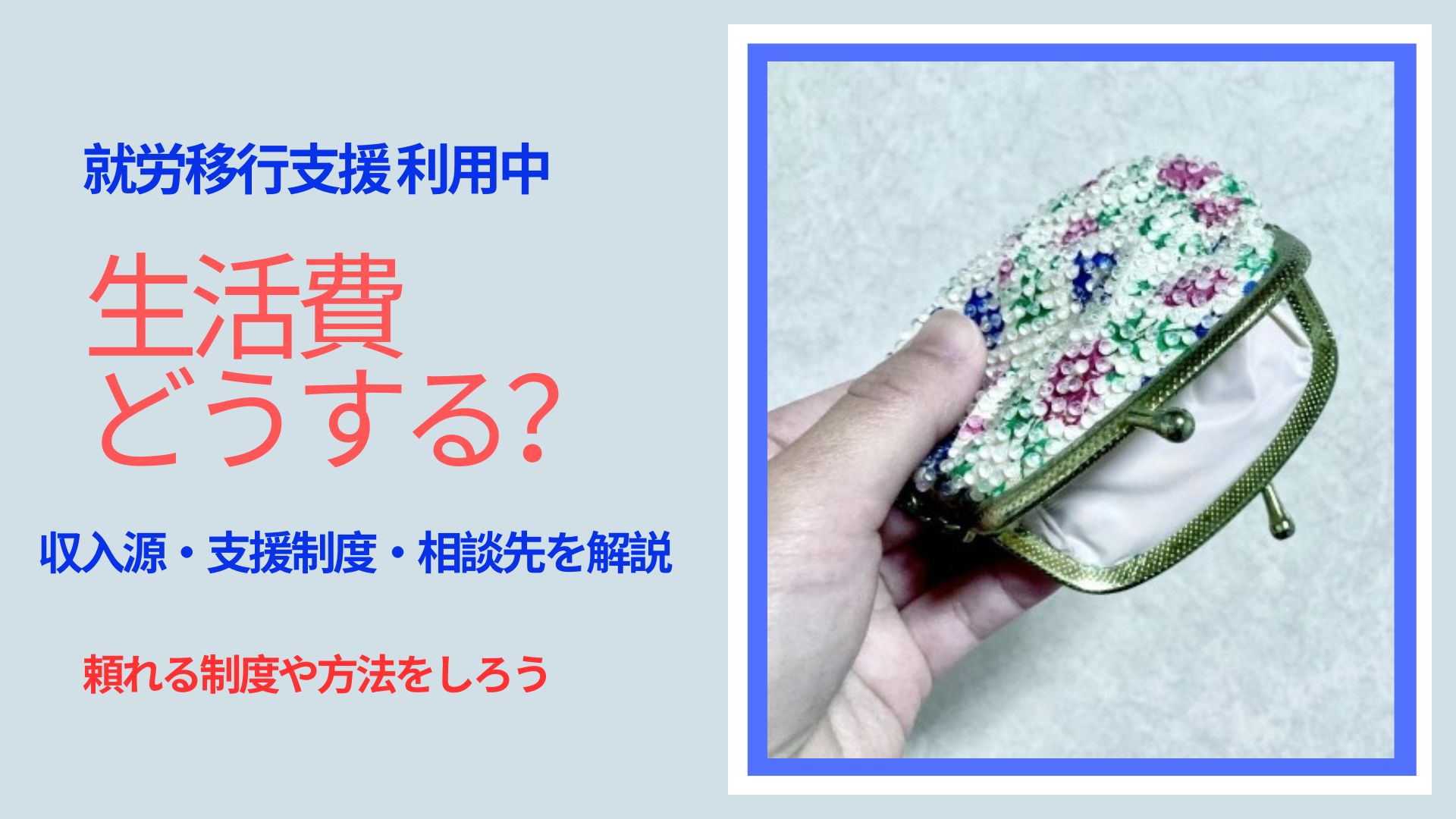
「就労移行支援中の生活費はどのように補えば良いのか」と不安を抱えていませんか。
就労移行支援では給与が発生しないため、収入がない状態で生活することに不安を感じるのは当然です。しかし、国や自治体の制度を利用したり、生活費を見直したりすることで、支援中の経済的な負担を軽減できる場合があります。

本記事では、就労移行支援中の生活費を支える収入源や、活用できる公的制度、困ったときの相談窓口を解説します。
>>> 目 次 <<<
1.就労移行支援を利用したいけど、生活費が心配
就労移行支援とは、心身の障がいや病気などで就職するのが難しい方に、就職に向けた訓練やサポートを行う障がい福祉サービスです。
障がいや難病を患っている方の中には「今のままでは働くのが難しい」と、再就職に対して不安を抱えている方も少なくありません。そうした状況に寄り添いながら、体調や特性に応じた支援を行っているのが就労移行支援です。
しかし、支援を利用する際に大きな壁となるのが、訓練期間中の生活費の確保です。
2.就労移行支援中の収入と生活費の基本的な考え方
就労移行支援は、あくまで就職に向けた訓練の場であるため、通所中は給与が発生しません。そのため、日々の生活費をどのように確保するか事前に考えておく必要があります。
収入源がないと聞くと「全て貯金で賄わなければならない」と思いがちですが、条件を満たせば、国や自治体の助成制度を利用できる場合があります。一人で抱え込まず、支援員や自治体の窓口、社会福祉協議会、家族などと相談しながら、生活費をどう確保するか決めておきましょう。
3.就労移行支援中の収入源には何がある? 頼れる制度や方法を知ろう

就労移行支援中であっても、毎月の生活費は変わらず必要です。あらかじめ収入源を確保しておくことで、経済的な負担を抑え、訓練に集中しやすくなります。
主な収入源には、以下の制度や手段が挙げられます。
- 障害年金
- 失業保険(雇用保険)
- 生活保護
- 貯金の活用と家族からの援助
- アルバイト
- その他(自治体の給付金など)
●障害年金
障害年金は、障がいや病気で働くことが難しい方に対して支給される年金です。制度には、国民年金に加入している方が対象の障害基礎年金と、厚生年金に加入している方が対象の障害厚生年金があります(※1)。それぞれ一定の条件を満たせば、障がいの等級に応じた年金が受け取れます。
ただし、医師の診断書や病歴を記載した書類を提出しなければなりません(※2)。事前に条件を確認し、必要に応じて社会保険労務士などに相談しながら手続きを進めましょう。
※1 参考:日本年金機構.「障害厚生年金を受けられるとき」(参照2025-05-04)
※2 参考:日本年金機構.「障害厚生年金を受けられるとき」(参照2025-05-04)
●失業保険(雇用保険)
失業保険(雇用保険)とは、勤務先を退職後、次の仕事が決まるまでの生活を保障する制度です。離職日から過去2年間のうちに、被保険者期間が通算12カ月以上(倒産・解雇などで離職を余儀なくされた受給資格者は直近1年間に通算6カ月以上)ある場合に利用できます(※1)。
支給額は、離職前6カ月間の賃金を基に算出した賃金日額の50~80%です(※2)。なお、自己都合で退職した場合は、給付開始までに約1~3カ月の待期期間があります(※3)。ご自身の待期期間を確認し、その間の収入源をどう補うか検討しておきましょう。
※1 参考:ハローワークインターネットサービス.「基本手当について」 (参照2025-05-04).
※2 参考:ハローワークインターネットサービス.「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」 (参照2025-05-04)
※3 参考:厚生労働省.「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について」p3.“令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について” (参照2025-05-04)
●生活保護
支援中の生活が立ち行かない場合は、生活保護の活用を検討しましょう。生活保護は、国が定めた最低生活費に対して収入が下回るときに、その差額を支給する制度です。医療費の免除や家賃、光熱費なども一部支給されるため、生活の立て直しを図る上で有効な制度です。
生活保護は、不動産や預貯金などの資産がなく、年金や手当などの給付金制度を活用しても必要な生活費を得られない方が受けられます。何らかの理由で就労できなかったり、就労しても生活がままならない方も対象です(※)。
※参考:厚生労働省.「生活保護制度」p1 (参照2025-05-04)
●貯金の活用と家族からの援助

貯金の活用や家族からの援助も検討しましょう。生活費を補える貯金があれば、一時的な経済的安定を維持できます。ただし、支出が続くと残高は徐々に減っていくため、使い過ぎないように注意する必要があります。
家族には、就労移行支援を受ける旨を伝えた上で、金銭面でのフォローが可能か相談してみましょう。家族からの援助があれば、経済的にも精神的にも負担が軽くなり、支援に専念しやすくなります。
●アルバイトは可能? 条件と注意点
就労移行支援中にアルバイトをするのは、原則禁止です。支援の対象となるのは、単独で就労するのが難しい人です(※)。そのため、アルバイトをしていると就労できると見なされ、支援を受けられなくなる可能性があります。
ただし、自治体や事業所によっては、一定の条件下でアルバイトが認められるケースもあります。個人で判断せず、事業所の支援員に相談してみましょう。
アルバイトが許可された場合は、訓練に支障が出ないよう無理のないスケジュールを組みましょう。
※参考:厚生労働省.「障害福祉サービスについて」(参照2025-05-04)
●その他(自治体の給付金など)
自治体によっては、就労に向けた支援として給付金制度を設けている場合があります。例えば、住居確保給付金は、離職・廃業後2年以内で住宅を失った、または失う恐れがある人に対し、家賃相当額(3カ月間・上限あり)を支給する制度です(※1)。
住宅を失っている場合は、臨時特例つなぎ資金貸付制度を活用すれば、上限10万円の貸し付けを受けられる可能性があります(※2)。
なお、貸付制度は指定の期限までに返済しなければなりません。給付金ではないため、注意しましょう。
※1 参考:厚生労働省.「住居確保給付金」 (参照2025-05-04)
※2 参考:厚生労働省.「臨時特例つなぎ資金貸付制度」p1(参照2025-05-04).
4.そもそも生活費はいくら必要?
就労移行支援を利用している間も、食費や光熱費などの生活費はかかります。
総務省の家計調査によると、2024年における単身世帯の1カ月当たりの平均的な消費支出は16万9,547円でした(※1)。2人以上の世帯では、2025年3月時点で33万9,232円となっています(※2)。
ただし、これらはあくまで全国平均の金額であり、地域や住環境、ライフスタイルによって必要な生活費は大きく変わります。就労支援を受ける前に、毎月の支出を把握しておきましょう。
※1 参考:e-Stat 政府統計の総合窓口.「家計調査 家計収支編 単身世帯」.”2024年 消費支出【円】” (参照2025-05-04)
※2 参考:総務省統計局.「家計調査報告 ―月・四半期・年―」.”家計調査(二人以上の世帯)2025年(令和7年)3月分(参照2025-05-21)(参照2025-05-04)
5.就労移行支援の利用にかかる費用と支援
就労移行支援は福祉サービスの一種ですが、利用に当たって費用が発生する場合があります。通所する本人や配偶者の収入が一定基準より少なければ無料で通所できますが、世帯収入が基準を超えていると、自己負担額が発生します。
以下で、就労移行支援の利用にかかる費用や交通費、昼食代の補助の有無を見ていきましょう。
●利用料は原則無料? 所得に応じた負担上限
就労移行支援の利用料は、世帯の所得に応じて以下の4つに分かれており、それぞれ負担上限額が決められています(※)。
| 区分 | 世帯の所得状況 | 負担上限額(月) |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 (収入が300万円以下の世帯) | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯 (収入が670万円以下の世帯) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外の世帯 | 3万7,200円 |
多くの方は生活保護世帯や低所得世帯に該当するため、自己負担なしで利用できるケースがほとんどです。
※参考:厚生労働省.「障害者の利用者負担」 (参照2025-05-04)
●事業所までの交通費や昼食代の補助は?
交通費や昼食代の補助の有無は、事業所や自治体によって異なります。例えば、静岡県浜松市では、条件を満たせば年間7,000円を上限とした交通費の補助を受けられます(※1)。
また、厚生労働省が平成30年に発表した調査によると、食事を提供している事業所は全体のうち66.5%でした(※2)。朝から夕方頃まで訓練を受けるケースが多いため、昼食を無料で提供している事業所も少なくありません。
経済的な負担を抑えるためにも、交通費や昼食代の補助があるかどうか確認しておきましょう。
※1 参考:浜松市.「〈新規〉障害者施設通所支援事業」 (2019-03-15)
※2参考:厚生労働省.「平成30年度障害者総合福祉推進事業食事提供体制加算等に関する実態調査報告書」p16.③食事(昼食)の提供状況について (参照2025-05-04)
6.生活費を抑える工夫

公的制度を活用したり、家族からの援助を受けたりするのも良い方法ですが、就労移行支援を受けている間は、できるだけ生活費を抑える意識も大切です。
ここでは、以下の3つのポイントに分けて、生活費を抑えるための工夫を紹介します。
- 固定費の見直し(家賃、通信費、保険料など)
- 変動費の節約(食費、交通費、娯楽費など)
- 障害者手帳などを活用した割引制度
●固定費の見直し(家賃、通信費、保険料など)
生活費に悩んでいるときは、毎月の固定費を見直してみましょう。家賃が負担になっている場合は、賃料が安い物件に引っ越したり、家族と同居したりするのも選択肢の一つです。
通信費は、格安スマートフォンへの乗り換えやプランの変更によって月々の負担を軽減できる場合があります。
保険料も、保障内容を見直すことで無駄な出費を抑えられる可能性があります。複数の保険に加入している方は、保障が重複していないか確認すると良いでしょう。
●変動費の節約(食費、交通費、娯楽費など)
固定費だけでなく、食費や交通費、娯楽費などの変動費も見直してみましょう。
例えば、外食を控えて自炊を心掛けるだけでも食費を節約できます。交通費は、定期券や回数券に変更すると出費を抑えやすくなります。割引券があれば、積極的に活用しましょう。徒歩や自転車で移動するのも、交通費の節約につながります。
娯楽費も、割引サービスを使えば節約可能です。その他、有料アプリを一時的に解約したり、自宅で楽しめる趣味を見つけるのも良いでしょう。
●障害者手帳などを活用した割引制度
障害者手帳を活用すると、交通機関の運賃割引や公共施設の利用料免除、携帯電話の割引など、さまざまな優遇措置を受けることが可能です。
例えば東京都では、障害者手帳を持っている方には、都営交通無料乗車券を発行しています。携帯電話は特定のプランの手数料が無料となったり、基本使用料が一定額割引となったりする場合があります。
他にも、精神障がいのかたは、自立支援医療制度(障がいを持っている方の医療費を軽減する制度)の適用で負担する医療費が3割から1割になるのもメリットです(※)。
※参考:厚生労働省.「自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み」p1 (参照2025-05-04)
7.どうしてもお金が足りない……そんなときの相談先と公的支援

生活費に不安を感じながら就労移行支援を受けるのは、精神的に大きな負担がかかります。どうしてもお金が足りないときは、一人で悩まず相談窓口や公的支援制度を活用しましょう。誰かに相談したり、支援制度を利用したりすれば、金銭面の不安を軽減できる可能性があります。
ここでは、経済的に困ったときに利用できる窓口や制度を紹介します。
●まずは相談! 頼れる窓口を知っておこう
支援中に生活費が足りなくなった場合に頼れる窓口は、以下の通りです。
- 就労移行支援事業所のスタッフ
- 自治体の障がい福祉窓口
- 障害者職業センター
- ハローワーク
- 生活困窮者自立支援窓口
- 相談支援事業所
これらの機関では、就労や生活に関する悩み相談を受け付けており、状況に応じた支援や生活費の援助を受けられます。中でも生活困窮者自立支援窓口では、生活の悩み相談だけでなく、住居確保給付金の支給や家計改善支援などを受けられます(※)。
※参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機関東京支部 東京障害者職業センター.「障害のある方へのサービス」 (参照2025-05-04).
※参考:WAM NET.「相談支援事業所」 (参照2025-05-04)
※参考: 厚生労働省.「生活困窮者自立支援制度」(参照2025-05-04)
●緊急時の公的な貸付制度
生活費をすぐに調達したいときは、総合支援資金の活用を検討するのも一つの手です。総合支援資金とは、生活を立て直すまでに必要な生活費を一定額貸し付ける制度です。
貸付項目と貸付上限額は、以下のように定められています(※)。
- 生活支援費:単身世帯月額15万円以内・複数世帯月額20万円以内の必要額
- 住居入居費:40万円以内の必要額
- 一時生活再建費:60万円以内の必要額
総合支援資金は給付金ではなく、借りた分だけ返済しなければなりません。返済が難しい場合は、他の公的制度の利用を検討しましょう。
※参考:東京都社会福祉協議会.「総合支援資金のご案内」p5 (参照2025-05-04)
8.まとめ
就労移行支援中の生活費に困ったら自治体や支援事業所に相談しよう

就労移行支援中に生活費が足りないと悩んだときは、一人で抱え込まず、失業保険や生活保護、障害年金などの公的制度の活用を検討しましょう。
お近くの行政、区役所の障がい福祉課、生活保護課、障害年金や自立支援医療制度の相談は主治医にする事も可能です。
また相談支援事業所をご利用で担当の方がいらしゃれば、そのような公的機関におつなぎしてくれたり、相談にのってくれることでしょう。
毎日の生活費に心配なく、障がい福祉サービスの就労移行支援を利用して、長く働ける仕事をみつけたいですね。
アクセスジョブでは、オーダーメイドの個別支援プログラムで、就労に向けたスキル習得や資格取得などのサポートを実施しています。一部事業所では、生活費を圧迫しがちな交通費や昼食代の補助も行っています。生活費を抑えながら手厚い支援を受けたいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
お問合せ:就労移行支援アクセスジョブ
オーダーメイドの個別支援プログラムで、障がいをお持ちの方の「働きたい」を実現します。資格取得プログラムやパソコン操作の基礎学習など、就職に役立つ多彩なカリキュラムを用意しています。

アクセスジョブの就労支援が少しでも気になったというかたは、ぜひ最寄りの事業所をチェックしてみてください。以下の「事業所を探す」からお探しいただけます。
就労移行支援を通して就職を目指したい方は、気になる事業所を見学してみるのがおすすめです。
メールによるお問い合わせも随時受け付けています。まずは気軽にお問い合わせください。
※1 参考:アクセスジョブ.「アクセスジョブとは」 (参照2025-04-30)
※2 参考:アクセスジョブ.「トップページ」 (参照2025-04-30)