
就労移行支援を利用してお金はもらえる? 費用と支援内容を解説
公開日:2025.07.09
更新日:2025.07.09

就労移行支援の利用を検討している方の中には、利用中の生活費に不安を感じている方も少なくないでしょう。
就労移行支援を利用すると、工賃や賃金などのお金をもらえるのでしょうか。
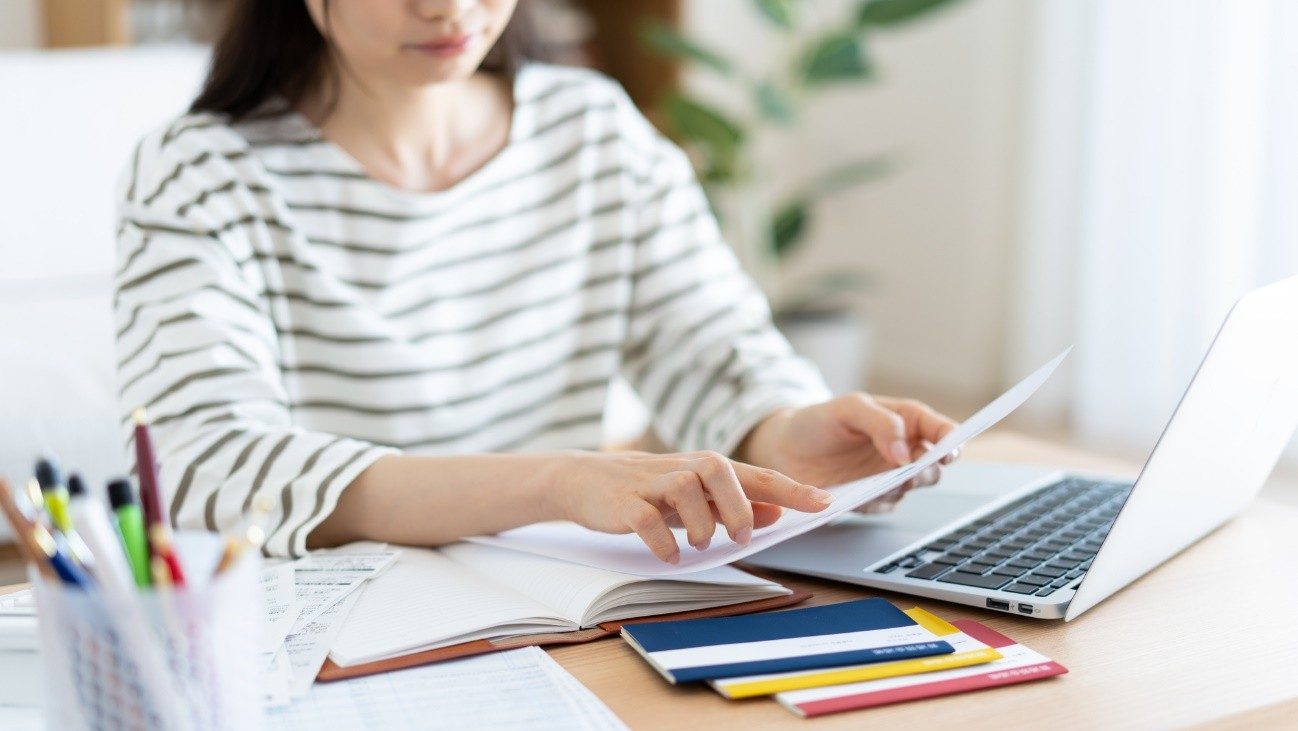
本記事では、就労移行支援の基本情報や工賃・賃金の有無、利用中にお金が発生する場面などを解説します。
就労移行支援の利用を検討しているものの、経済的な不安がある方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
>>> 目 次 <<<
1.就労移行支援とは?
就労移行支援とは、障がいや難病を抱えている方が、一般企業などでの就労(一般就労)を実現できるように支援を行う障がい福祉サービスです。

就労移行支援を利用すると、就労移行支援事業所に通いながら、職業トレーニングや企業での実習などを受けられます。
就職に向けたマナーや身だしなみの習得、履歴書の作成、模擬面接などのサポートを受けられ、ハローワークと連携しながら就職先を探してもらえます。
また就職後も定期的に事業所の面談を受けながら、就職先に定着できるように支援を受けることが可能です。
65歳未満の方を対象としており、利用期間は原則2年間です(※)。身体障がい・知的障がい・精神障がい・発達障がい・難病があり、一般企業への就職や、在宅での就労や起業を希望している方がサービスを利用できます。
※参考:厚生労働省.「就労移行支援事業」 (参照 2025-04-30)
2.就労移行支援における賃金の支払い
就労移行支援の利用を検討している方の中には、お金への不安を感じている方も多いのではないでしょうか。ここからは、就労移行支援の賃金や工賃などについて解説します。
●工賃とは?
一般的に工賃とは、物を生産・製作・加工する際の労力に対して支払われる手間賃を意味します。
福祉分野で工賃とは、一般的な雇用契約を結んで就労することが難しい方が、就労支援を通して行った作業(製造・事務など)に対して支払われるお金です。
工賃は、作業によって得られた収益から材料費や消耗品費、水道光熱費などの必要経費を差し引いた額を、作業に関わった人たちで分配します。一般的な雇用契約を結んでいないため、賃金とは見なされません。
●就労移行支援事業所では原則、賃金・工賃の支払いはない
就労移行支援事業所では、原則、賃金や工賃の支払いはありません。

これは、就労移行支援が働いてお金を稼ぐことを目的とするのではなく、一般就労を実現するためにスキルや知識を身に付けることや、就職活動のサポートを行うことを目的としているからです。
就労移行支援事業所は、いわゆる「学校」のような位置付けとなります。そのため、工賃が支払われないのが一般的です。
●例外とされるケースは?
前述した通り、就労移行支援事業所では工賃が支払われませんが、例外として工賃が支給されるケースもあります。
就労移行支援事業所の中には、作業を行い、対価としてお金をもらうことを通して、仕事へのやりがいや達成感、責任などを感じてもらうことを目的に、工賃を支払っているところがあります。また金銭管理の感覚を身に付けるという目的もあります。
ただし金銭の支給がある場合でも、月に数千円程度しか支払われません。そのため、工賃の有無で通所する就労移行支援事業所を選ぶよりも、学べる内容やサポートの充実度、就職率などを重視するのがおすすめです。
3.就労移行支援を利用する間の収入源

原則として就労移行支援事業所では工賃が支払われないため、経済的な不安がネックとなって、サービスの利用をちゅうちょする方もいるかもしれません。就労移行支援を利用している方は、どのように生活費を確保しているのでしょうか。
ここからは、就労移行支援を利用している間の主な収入源を解説します。
●障害年金
障害年金の請求(申請)をすると、就労移行支援を利用中の収入源にできます。障害年金とは、病気やけがなどが原因で、生活や仕事に支障が出ている方に支給される年金です。
「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があり、前者は障がいの原因となった病気やけがで初めて医療機関を受診した際に国民年金に加入していた方、後者は厚生年金に加入していた方が受給できます。
年金というと高齢者が受給できるものという印象があるかもしれませんが、障害基礎年金は原則20〜64歳まで、障害厚生年金は加入していれば年齢に関係なく請求できる点が特徴です(※)。
ほとんどの傷病が対象となっており、受給できるかどうかに障害者手帳の有無は関係ありません。
受け取れる年金額は年金の種類や障がいの等級、受給期間は障がいの種類などによって異なります。詳細は、日本年金機構やお住まいの地域を管轄する年金事務所に確認しましょう。
※参考:NPO法人 障害年金支援ネットワーク.「よくある質問」 (参照 2025-04-30)
●雇用保険(失業保険)の基本手当(失業給付金)
就労移行支援の利用中に、雇用保険の基本手当を受け取って収入源とすることも可能です。
雇用保険の基本手当は、雇用保険に加入していた方が何らかの理由で離職した際に、失業中の経済的な不安なく、再就職を目指せるように支給される手当です。失業給付金とも呼ばれます。

給付される期間は被保険者であった期間と年齢によって異なります。障がいがある方で「就職困難者」として認定されれば、年齢や雇用保険の加入期間に応じて、150〜300日間、基本手当を受給することが可能です。
支給期間が延びる可能性がありますので、ハローワークでの失業手当の申請時に必ず「障害者手帳」を提示しましょう。
雇用保険の基本手当は、離職票を提出し、求職の申し込みをした日から7日間の待期期間を経た後、支給が開始されます。ただし、自己都合で退職した場合、待期期間終了後1~3カ月間は支給が開始されません(※2)。
雇用保険の基本手当に関する相談や手続きの方法などは、お住まいの地域を管轄するハローワークにお問い合わせください。
※参考:ハローワークインターネットサービス.「よくあるご質問(雇用保険について)」 (参照 2025-04-30)
※参考:厚生労働省.「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」 (参照 2025-05-20)
●傷病手当金
傷病手当金とは、会社員や公務員で健康保険に加入している方が、病気やけがで働けなくなった際に受給できる手当です。

会社を辞めても支給開始日から通算1年6カ月まで受給できるため、就労移行支援利用中も受け取ることができます(※)。ただし、雇用保険の基本手当との併用はできないため、注意が必要です。
傷病手当金の詳細や申請方法などは、加入している健康保険組合にお問い合わせください。
なお、自営業の方などで国民健康保険に加入している場合は、原則として傷病手当金の支給はありません。
※参考:全国健康保険協会.「病気やケガで会社を休んだとき」 (参照 2025-04-30).
●生活保護

生活保護は、生活に困窮している方を対象として、健康で文化的な最低限度の生活を支えることを目的に、生活費や支援を提供する制度です(※)。
障がいがあるかどうかに関係なく受給できますが、資産や貯金の有無、家族・親族からの援助が見込めるかどうかなどが考慮されます。
就労移行支援を利用して就職した場合も、規定額より収入が低い場合は、差額を生活保護で受け取ることも可能です。
生活保護の受給条件や申請などについては、お住まいの地域を管轄している福祉事務所の生活保護担当にご確認ください。
※参考:厚生労働省.「生活保護制度」 (参照2025-05-01).
●家族の援助
就労移行支援利用中に家族からの援助を受けられる場合は、検討してみましょう。
家族の援助が受けられる場合、他の収入源や生活費サポートと違って、申請などの必要がないため、就労移行支援に集中して取り組みやすいでしょう。
援助が受けられるかどうかは家庭の事情によって異なりますが、一度相談してみるのも一つの方法です。
4.就労移行支援を利用しながらアルバイトはできる?
「就労移行支援利用中の生活が不安だから、アルバイトをしよう」と、考えている方もいるかもしれません。

しかし原則として、就労移行支援利用中はアルバイトができないことになっています。アルバイトが原則禁止となっているのは、就労移行支援が、就労を希望する方で、自力での就労が難しい方を対象としたサービスだからです。
アルバイトができる状態の方は、就労移行支援を受ける必要がないと判断される可能性があります。
●自治体の判断によりアルバイトが可能なケースもある
原則として就労移行支援利用中のアルバイトは禁止ですが、自治体によってはアルバイトが認められることもあります。
アルバイトが認められるかどうかは、自治体によって判断が異なるため、希望する場合は各自治体の障害福祉窓口に問い合わせてみましょう。ただし、アルバイトが認められる場合も、基本的には労働日数や労働時間に制限があります。
5.就労移行支援でお金がかかる場面は?
就労移行支援を利用している間、どのような場面で出費が必要になるのでしょうか。お金がかかる代表的な場面を3つご紹介します。
●就労移行支援の利用料金
就労移行支援を利用する場合、サービスの利用料金が発生することがあります。
利用料金は一律ではなく、前年度の世帯年収(利用者本人と配偶者の前年度の所得)で分けられた4つの区分に応じて、自己負担額の上限が決まるのが特徴です。

生活保護を受給している世帯や市町村民税が非課税の世帯は、利用料金の自己負担額の上限は0円です。市町村民税非課税世帯は、所得や扶養人数によって決められています。
例えば、3人世帯で障害基礎年金1級を受給している場合、前年度の世帯年収がおおむね300万円以下の世帯は、市町村民税非課税世帯です。
世帯年収がおおむね300万円以上の世帯は、市町村民税課税世帯に該当し、毎月の利用料金の自己負担額の上限が設けられています。
この場合、前年度の世帯年収がおおむね670万円以下かどうかで、利用料金の自己負担額の上限が変わってくるため注意が必要です。
例えば世帯年収が350万円の場合、利用料金の自己負担額の上限は、9,300円となります。
前年度の世帯年収が700万円の場合は、利用料金の自己負担額の上限は3万7,200円です(※)。
なお事業所の利用料金は、通所1回ごとに発生する仕組みです。1回の利用料金は約500〜1,200円となっています。例えば、1回の利用が1,000円の事業所に、月20回通う場合、利用料金は「1,000円 × 20回 = 2万円」です。

前年度の世帯年収がおおむね670万円以下の方は、2万円の利用料金のうち、自己負担額の上限である9,300円を支払うことになります。
前年度の世帯年収がおおむね670万円以上の方は、2万円の利用料金全額を支払います。生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯の場合、自己負担額の上限は0円であるため、利用料金は発生しません。
ただし、ここでご紹介した区分ごとの世帯年収はあくまで目安です。ご自身がどの区分に該当するかは、自治体の障害福祉窓口にお問い合わせください。
※参考:厚生労働省.「障害者の利用者負担」 (参照 2025-04-30)
●交通費
就労移行支援を利用する際は、就労移行支援事業所に通うための交通費も発生します。また、企業見学や企業実習に参加する際の交通費、就職活動で面接などに行く場合の交通費も自己負担です。
ただし、就労移行支援事業所によっては、交通費が一部支給されることもあります。加えて、就労移行支援利用中の負担軽減を目的とした補助制度を利用できることもあります。
●食事代
お昼をまたいで就労移行支援事業所でトレーニングを受けたり実習に参加したりする場合などは、昼食代や間食代も必要です。食事代にかかる費用も、補助制度を利用できることがあります。
6.お金をもらいながら就労支援を受けたい方は
お金をもらいながら就労支援を受けたい方は、就労継続支援の利用を検討するのも一つの方法です。
就労継続支援も、障がい福祉サービスの一環です。障がいや難病によって一般就労が困難な方を対象として、就労機会・生産活動機会を提供します。
就労移行支援同様、前年度の世帯年収で分けられた4つの区分に応じて、自己負担額の上限がかかりますが、賃金や工賃が支払われるのが特徴です。利用期間に制限はありません。
就労継続支援には「就労継続支援A型事業」と「就労継続支援B型事業」があります。
それぞれどのような事業なのかを見ていきましょう。
●就労継続支援A型事業
就労継続支援A型事業は、雇用契約を結んで働くことが可能なものの、障がいや難病などにより一般就労や就労移行支援の利用が難しい方を対象とした支援事業です。サービスの利用開始時に65歳未満の方が利用できます(※1)。

雇用契約を結んで働くため、法律に基づいて最低賃金が保証されているのが特徴です。主に以下のような仕事に携わります。
- データ入力
- 飲食店での接客
- Web制作
- 商品の梱包・発送
- 清掃業務
- 部品などの加工業務
就労継続支援A型事業を利用した方の2022年度の賃金の平均は、8万3,551円/月でした(※2)。
※1 参考:厚生労働省.「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」 (参照2014-09-25)
※2 参考:厚生労働省.「令和4年度工賃(賃金)の実績について」 (参照 2025-04-30)
●就労継続支援B型事業
就労継続支援B型事業は、障がいや難病などにより、雇用契約を結んで働くことが難しい方を対象とした支援事業です。

原則として、サービスの利用に年齢制限はありません。就労継続支援A型事業の利用が難しい方でも、利用できます。
就労継続支援A型事業と異なり、雇用契約を結ばないため、賃金ではなく工賃が支払われるのが特徴です。主に以下のような作業を行います。
- 部品の加工
- 農作業
- 食品の製造・販売
- ピッキング
- 梱包・袋詰め
- 衣類のクリーニング
就労継続支援B型事業を利用した方の2022年度の工賃の平均は、1万7,031円でした(※)。就労継続支援A型事業と比較すると、得られる工賃の平均は低くなりますが、労働日数や労働時間に融通が効きやすいため、無理なく働くことができます。
※参考:厚生労働省.「令和4年度工賃(賃金)の実績について」 (参照 2025-04-30)
7.【まとめ】就労移行支援を利用して一般就労を実現しよう
就労移行支援の利用中、原則として工賃や賃金は支払われません。
しかし職業訓練や実習、就職活動支援などを受けることで、ご自身に合った一般就労の実現が目指せます。

障害年金や雇用保険の基本手当など、就労移行支援の利用中に活用できる制度もあるため、経済的に不安がある方は、ご自身が活用できる制度を確認しておくことも大切です。
これまでに600件以上の就職実績がある就労移行支援事業所「アクセスジョブ」は、全国に複数の事業所を展開しています。
交通費助成やランチ応援制度を行っている事業所もあるため、経済的に負担がある方もぜひ一度ご相談ください。
お問合せ:就労移行支援アクセスジョブ
アクセスジョブでは、オーダーメイドの個別支援プログラムで、障がいをお持ちの方の「働きたい」を実現します。資格取得プログラムやパソコン操作の基礎学習など、就職に役立つ多彩なカリキュラムを用意しています。

アクセスジョブの就労支援が少しでも気になったというかたは、ぜひ最寄りの事業所をチェックしてみてください。以下の「事業所を探す」からお探しいただけます。
就労移行支援を通して就職を目指したい方は、気になる事業所を見学してみるのがおすすめです。
メールによるお問い合わせも随時受け付けています。まずは気軽にお問い合わせください。
※1 参考:アクセスジョブ.「アクセスジョブとは」 (参照2025-04-30)
※2 参考:アクセスジョブ.「トップページ」 (参照2025-04-30)