
就労移行支援を利用しても就職できなかったときの対応とその解決方法を解説
公開日:2025.07.14
更新日:2025.07.14
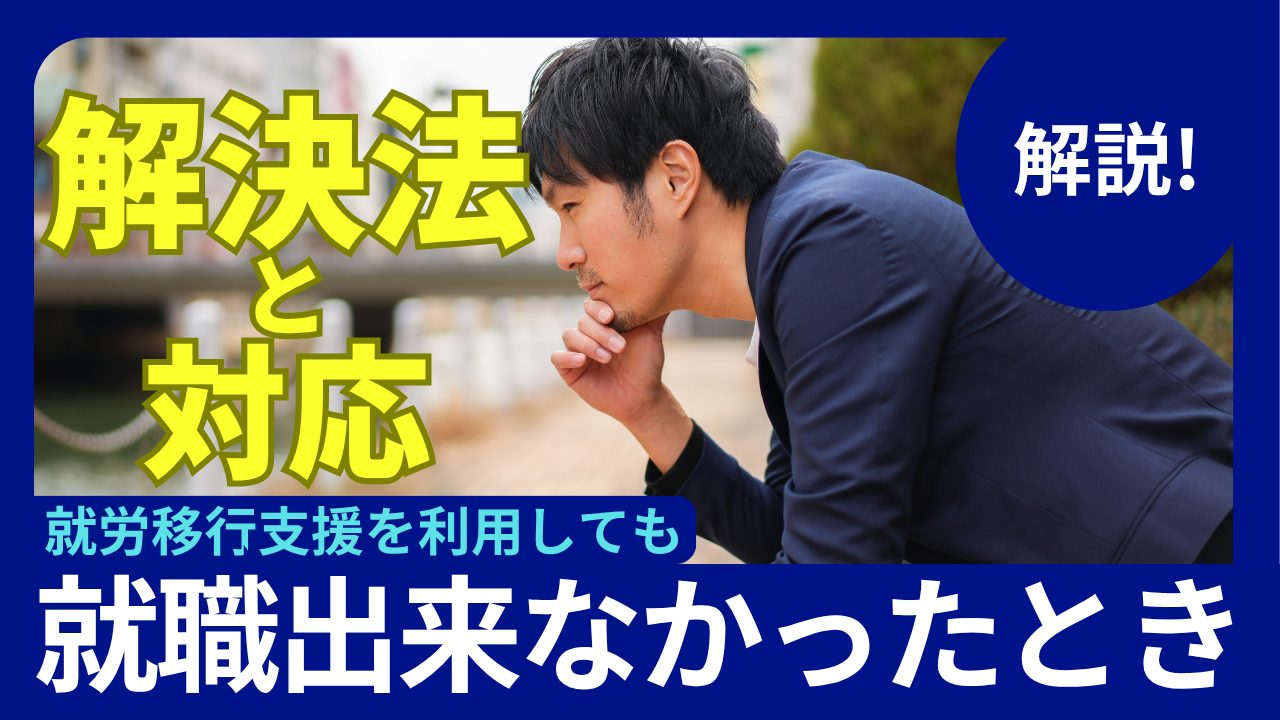
就労移行支援は、障がいや難病を抱えている方が一般企業への就職を目指す際に、その実現に向けたサポートを受けられる障がい福祉サービスです。
ただし、利用期間は原則2年間と定められており、期間内に就職に至らないケースもあります(※)。

就労移行支援を利用している方の中には、「利用終了までに就職できるか不安」という方もいるでしょう。また、本当に就職できるかが不安で、利用を躊躇している方もいるかもしれません。
しかし、サービス利用後すぐに就職できなかった場合は、就職を目指すための多様なアプローチ方法があります。
本記事では、就労移行支援を利用しても就職に至らなかった場合の対応策や解決方法について解説します。不安を感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。
>>>目次<<<
※参考:厚生労働省.「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」 (参照2014-09-25)
1.就労移行支援を利用しても就職できない場合の対応方法とは?
就労移行支援を利用しても、就職が実現しなかった場合、どのような対応をすれば良いのでしょうか。6つの対応方法を解説します。

①就労移行支援制度の延長申請をする
就労移行支援の利用期間中に就職が難しそうな場合は、サービス期間の延長を申請しましょう。
就労移行支援の利用期間は、原則2年間と定められています。しかし、やむを得ない事情があると自治体に認められた場合、最大1年間の延長が可能です(※)。以下のようなケースは、延長を認められる可能性があります。
- 延長することで就職できる見込みがある
- 職場実習中に利用期間が終了する
- 利用期間終了後に新たな職場実習の予定がある
必ずしも延長が認められるわけではありませんが、延長を希望する場合は、事業所の担当者に相談して申請しましょう。延長申請は利用期間終了前にする必要があるので、早めに相談してください。
※参考:厚生労働省.「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」 (参照2024-03-29)
②就労継続支援A型・B型に移行する
就労移行支援を利用して就職に至らなかった場合、就労継続支援A型・B型に移行するのも一つの方法です。
就労継続支援は、障がいや難病を抱えている方に、雇用または就労の機会を提供する障がい福祉サービスです。就労移行支援は基本的に給与や工賃は支払われませんが、就労継続支援は実際に働き、対価として給与や報酬が支払われます。就労継続支援を利用しながら、一般企業への就職を目指すことも可能です。
就労移行支援事業所の69%は、就労継続支援事業所を併設しているところもあります。そのため、現在利用中の事業所で、そのまま就労継続支援を受けられるケースもあります(※)。
※参考:厚生労働省.「第15回 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 議事次第(オンライン会議)」(参照2020-09-24)

③職業訓練制度を利用する
就労移行支援を利用しても就職に至らなかった場合、職業訓練制度を利用するのも一つの選択肢です。
職業訓練制度とは、再就職や転職を目指す方に向けて、一般企業で働くために必要な知識やスキルを身に付けるための職業訓練を、無料で提供する制度です。職業訓練制度には、以下の2つの種類があります。
- 公共職業訓練:雇用保険の受給ができる方を対象とした訓練
- 求職者支援訓練:雇用保険の受給ができない方を対象とした訓練
求職者支援訓練の場合、一定条件を満たすと、生活支援として月額10万円を受給しながら、職業訓練・就職支援も受けることが可能です(※)。
職業訓練制度を利用するためには、ハローワークへの登録が必要です。訓練コースにはさまざまな種類がありますが、自治体によってコース内容が異なるので、詳しくはハローワークでご確認ください。
職業訓練を通して習得したスキルや知識は、就職活動でアピールする強みになるでしょう。
※参考:厚生労働省.「求職者支援制度のご案内」(参照2025-05-15).
④自力で就職活動をする

就労移行支援を利用して就職できなかった場合、自分で就職活動をすることも検討しましょう。
自分で就職する場合、ハローワークや民間の求人サイトを活用するのが一般的です。
障がい者雇用を積極的に行っている企業も増えているので、ご自身に合う企業が見つかる可能性は十分にあります。
全国のハローワークには、障がいのある方を対象とした専門の相談窓口が設けられています。自力で就職を目指す場合は、まず相談してみると良いでしょう。
能力や障がいの特性によっては、障がい者雇用枠だけでなく、一般枠での就職を目指すことも可能です。
⑤転職エージェントを利用する
自力での就職活動に不安がある方は、転職エージェントの利用も検討してみましょう。
転職エージェントとは、企業と求職者を仲介し、転職支援を行ってくれるサービスです。転職エージェントの中には、障がいがある方の就職支援を専門に行っているところもあります。
転職エージェントを利用することで、以下のようなサポートが受けられます。
- 一人ひとりに合った求人の紹介
- 履歴書・職務経歴書の添削
- 面接練習や企業との日程調整
- 入社後のサポート
ハローワークなど、自治体のサービスと転職エージェントを併用することも可能です。
⑥いったん就職活動を休んでみる

就労移行支援を経ても就職できなかった場合、いったん就職活動を休むという選択肢もあります。
職業訓練や就職活動を頑張って、「少し休みたい」「自分の将来をじっくり考えたい」という方もいるでしょう。
焦りや不安を抱えたまま無理に就職活動を続けると、心身に大きな負担がかかる可能性があります。いったん休んで、気持ちをリセットすることも大切です。
休んでいる間に独学でスキルアップすることもできます。一度休んで態勢を立て直した後に、再び就職を目指すと良いでしょう。
2.就労継続支援A型とは?
就労継続支援A型とは、障がいや難病を抱えている方で、一般企業への就職は難しいものの、雇用契約を結んで働ける65歳未満の方を対象にした障がい福祉サービスです(※1)。
主に以下のような方を対象としています。
- 就労移行支援を受けたが、一般企業への就職が実現しなかった
- 雇用契約を結んで働くことは可能だが、一般企業への就職が難しい
- 一般企業で働いていたが、現在は離職している
就労移行支援と異なり、就労の機会の提供を主な目的としているのが特徴です。
ただし、一般企業への就職を希望している方は、サービスの利用を通して、就労に必要なスキルや知識が身に付けられるように、支援を受けられます。

事業所にもよりますが、週5日程度出勤し、1日4〜8時間程度働くケースが一般的です。
ただし、最初は短時間からスタートするなど、勤務条件などは柔軟に相談できます。障がいの特性や病気による体調不良などに対する配慮を受けながら、自分のペースで就労経験を積めるでしょう。
就労移行支援と異なり、利用期間の制限はありません。雇用契約を結んで働くので、最低賃金以上の給与が保証されています。
2023年度における就労継続支援A型の月額平均給与は、86,752円でした(※2)。
事業所によって、働く場所や職種はさまざまですが、仕事の一例としては、データ入力や飲食店のホールスタッフ、パン・お菓子の製造などがあります。
※参考:厚生労働省.「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」 (参照2024-03-29)
※2 参考:厚生労働省.「令和5年度工賃(賃金)の実績について」 (参照2025-05-15)
3.就労継続支援B型とは?

就労継続支援B型は、障がいや難病を抱えている方で、一般企業への就職が難しく、雇用契約を結んでの就業も困難な方を対象とした障がい福祉サービスです。
年齢制限はなく、主に以下のような方を対象としています。
- 就労経験はあるが、年齢や体力の問題により、これまでと同じ働き方が難しくなった
- 就労移行支援を利用したが、就労継続支援B型が適していると判断された
- 上記に該当しない方で、50歳以上の方または障害基礎年金1級を受給している方(※1)
就労継続支援A型同様、主に就労の機会が提供されます。サービスの利用によって、知識やスキルを身に付け、一般企業への就職を目指すことも可能です。
ただし、雇用契約は結ばないため、最低賃金は保証されていません。労働の対価として、作業や内容に応じた工賃が支払われます。
2023年度における就労継続支援B型の月額平均工賃は、23,053円でした(※2)。
仕事内容は、事業所によって異なりますが、農作業やパン・菓子の製造、手工芸、清掃業務などがあります。
出勤日数や勤務時間が柔軟なので、ご自身の特性や体調に合わせて、調整しながら働けるのが特徴です。
2018年に日本財団が実施した調査によると、週当たりの就労時間の平均値は22 時間でした(※3)。週当たりの就労時間は個人差が大きく、5時間未満の方もいれば、50時間以上働く方もいます。
※参考:厚生労働省.「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」 (参照2024-03-29)
※2 参考:厚生労働省.「令和5年度工賃(賃金)の実績について」 (参照2025-05-15)
※3 参考:日本財団.「レポート 平均工賃に関するいくつかの論点について」 (参照2018-06-12)
4.就労移行支援制度以外に利用できる制度やサービス
就労移行支援制度以外にも、障がいや難病を抱える方が利用できる就労支援制度・サービスにはさまざまなものがあります。ご自身に合う就労を実現するために、その他の制度やサービスに関しても把握しておきましょう。

●ハローワーク
ハローワーク(公共職業安定所)とは、国が無償で提供する雇用サービス機関です。全国に544カ所の拠点があり、求人紹介を行う他、雇用保険や職業体験などの制度も管轄しています(※)。
ハローワークには障がいがある方の就職を支援するための専門の相談窓口があります。ハローワークの職員の他、福祉施設の職員やその他の就労支援者などがチームを組んで、就職から職場への定着までワンストップで支援してくれるのが特徴です。2024年度は、ハローワーク経由で67.7万人の障がい者の方が就職を実現しています(※)。
※参考:.厚生労働省 職業安定局.「公共職業安定所(ハローワーク)の主な取組と実績(令和7年4月)」 (参照2025-05-15)
●ハロートレーニング(障がい者訓練)
ハロートレーニング(障がい者訓練)は、障がいを抱える方を対象として、状況に応じたサポートを行いながら、職業訓練を提供する国の制度です。
訓練の種類は、以下のようなものがあります。
- 一般校での障がい者職業訓練
- 障がい者能力開発校における職業訓練
- 障がいがある方のニーズに応じた多様な委託訓練
2023年度の受講者数と就職率は、以下のようになっています。
| 受講者数 | 就職率 | |
| 障がい者職業能力開発校における職業訓練(離職者訓練) | 1,244人 | 68.9% |
| 一般校における障がい者職業訓練 | 756人 | 73.6% |
| 障がい者の多様なニーズに対応した委託訓練(離職者訓練) | 2,588人 | 40.4% |
(※)
制度を利用する際は、ハローワークでの求職者登録が必要です。訓練終了後は、ハローワークの障がい者専門窓口で、就職支援を受けることもできます。
※参考:厚生労働省.「公共職業訓練(障害者訓練)の実施状況」 (参照2025-05-15)

●職業リハビリテーションセンター
職業リハビリテーションセンターは、厚生労働省が設置し、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が運営している国立の施設です。一人ひとりの障がいや病気の状況に応じて、職業訓練や職業指導を行い、就職の実現を支援するのが特徴です。
職業リハビリテーションセンターは全国に2カ所設置されています。
- 埼玉県所沢市:国立職業リハビリテーションセンター
- 岡山県加賀郡吉備中央町:国立吉備高原職業リハビリテーションセンター
埼玉県の職業リハビリテーションセンターは、短期コースが6カ月、標準コースが1年、岡山県の職業リハビリテーションセンターは1年間もしくは2年間のコースが用意されています。
週5日、1日6〜8時間程度の職業訓練を受講します(※1)(※2)。ご自宅が施設から遠い場合は、隣接する宿舎に入居して通うことも可能です。
就職が内定した場合は、担当する業務や職場環境などに合わせたトレーニングを受けられます。
※1 参考:国立職業リハビリテーションセンター.「入所申請から入所まで」 (参照2025-05-15)
※2 参考:国立吉備高原職業リハビリテーションセンター.「募集対象者」 (参照2025-05-15)

●障がい者職業能力開発校
障がい者職業能力開発校とは、障がいがある方を対象とした職業訓練が受けられる学校です。国や自治体が設置し、自治体が運営しています。
訓練を通したスキルや知識を習得し、就職支援、職場への定着支援などを受けることが可能です。学校によって設置されているコースは異なりますが、基本的に学べる内容に大きな違いはありません。障がいの種類によって、受講できるコースが決められています。
ただし、障がい者職業能力開発校は、全ての都道府県に設置されているわけではありません。自宅から遠い場合は、家賃・光熱費が無料の寮に入り、学校に通うこともできます。
●一般の公共能力開発校の障がい者対象訓練科
公共能力開発校の中には、障がい者を対象とした職業訓練を行っているところもあります。
公共能力開発学校は、離職者や求職者を対象にした職業訓練校です。
2024年4月時点で、全国に都道府県が設置している学校は145校、市町村が設置している学校は1校あります(※)。
6カ月から1年程度をかけて、職業訓練を行います。学校によって入校の時期は異なりますが、多くの場合、入校時期は4月または10月です。タイミングによってはすぐに入校できない可能性があるので、希望する場合は、事前にハローワークに相談しておくと良いでしょう。
※参考:.厚生労働省.「公共職業能力開発施設について」(参照2025-05-15)
●障がい者委託訓練事業
障がい者委託訓練事業は、都道府県が主体となり、障がいのある方のスキルや知識の習得を支援する事業です。
近隣に障がい者職業能力開発校がない方でも気軽に職業訓練が受けられるよう、外部機関に委託されています。訓練の実施先は以下の機関です。
- 一般企業
- 社会福祉法人
- NPO法人
- 民間教育訓練機関
訓練期間は原則3カ月以内、受講時間は月100時間程度となっています(※)。eラーニングコースも開講されているので、通学が難しい方でも職業訓練を受けられます。
※参考:厚生労働省.「障害者の多様なニーズに対応した委託訓練」(参照2025-05-15)

●地域障がい者職業センター
地域障がい者職業センターは、障がいを抱える方に対して、職業リハビリテーションを実施する施設です。
職業紹介はしていませんが、ハローワークと連携し、就職に必要なさまざまなサポートを行います。
職業リハビリテーションセンターは全国に2カ所しかありませんが、地域障がい者職業センターは各都道府県に設置されています。障がい者手帳の有無にかかわらず、無料で利用可能です。
就労に向けたスキルや知識の習得だけではありません。
ヒアリングをもとに職業リハビリテーション計画を立て、一人ひとりに合った支援を行いながら、就職を目指せます。
就職後は職場にジョブコーチが派遣され、就職した方と雇用主に対して、職場への定着も支援してくれるのが特徴です。
精神的な不調によって現在離職している方に対しては、リワーク(職場復帰)支援も実施しています。復職後も体調を安定させて働けるように、自己管理を支援する他、復職に向けたさまざまな準備にも対応してくれます。
●障がい者就業・生活支援センター
障がい者就業・生活支援センターは、障がいのある方の雇用を促進する目的で、全国に設置されている施設のことです。
就職を実現し、仕事と日常生活において自立ができるよう、雇用・保険・福祉・教育などの関連機関と連携した支援を行っています。
就職活動だけでなく、体調管理や金銭管理、住まいや余暇の過ごし方なども総合的にサポートするのが特徴です。
前述した地域障がい者職業センターは、障がいのある方と雇用主を対象として、専門的なサポートを実施する施設です。
一方、障がい者就業・生活支援センターは障がいのある方を対象として、地域に密着した支援を行います。2025年4月1日時点で全国に338カ所の障がい者就業・生活支援センターがあるので、ご自宅から通いやすい施設を見つけやすいでしょう(※)。
※参考:厚生労働省.「障害者就業・生活支援センターについて」 (参照2025-05-15)
5.【まとめ】就労移行支援で就職できなくても、いろいろな選択肢がある
就労移行支援は原則2年間の利用期間が定められているため、その間に就職がかなうとは限りません。もし利用期間が終了する前であれば、延長申請という選択肢があります。期間内に就職が難しいと感じた場合は、事業所の担当者に早めに相談しましょう。

「今の事業所が合わない」と感じた場合は、変更を検討するのも一つの方法です。あなたに合った支援が受けられる環境を選ぶことで、就職支援の効果を高められます。
自分に合う事業所を見つけるためには、複数の事業所を見学・体験して比較することも大切です。実際の雰囲気やスタッフの対応を見ることで、「ここならがんばれそう」と思える場所に出会えるかもしれません。
今回ご紹介したように、就労移行支援が終わった後にも、さまざまな支援制度があります。
- 就労継続支援A型・B型の利用
- 職業訓練や委託訓練の活用
- 転職エージェントやハローワークでの支援
- 地域センターでの相談や生活支援の活用
何よりも大切なのは、お一人で悩まず、まずは誰かに相談してみることです。
事業所の担当者はもちろん、地域の支援機関やセンターなど、さまざまな相談窓口があります。
誰かに話を聞いてもらうことで、ご自身に必要な支援が見えてくる可能性もあります。もし、見学や体験に不安を感じるようでしたら、メールで事業所に問い合わせることも可能です。
「事業所を変えたい」「自分に合う事業所を見つけたい」という方は、まず相談してみましょう。

「アクセスジョブ」は、教育・福祉分野で50年の実績を持つクラ・ゼミグループが運営する就労移行支援事業所です(※)。
これまで600名以上の方の就職をサポートしてきました(※)。一人ひとりの希望や目標に合わせ、オーダーメイドの個別支援プログラムを提供しているのが特徴です。
状況や体調によっては、在宅で訓練を受けていただくこともできます。経験豊富なスタッフが、就職に向けてしっかりサポートしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。見学や体験も随時受け付けています。
※参考:アクセスジョブ.「トップページ」 (参照2025-05-15)
お問合せ:就労移行支援アクセスジョブ
アクセスジョブでは、オーダーメイドの個別支援プログラムで、障がいをお持ちの方の「働きたい」を実現します。資格取得プログラムやパソコン操作の基礎学習など、就職に役立つ多彩なカリキュラムを用意しています。

アクセスジョブの就労支援が少しでも気になったというかたは、ぜひ最寄りの事業所をチェックしてみてください。以下の「事業所を探す」からお探しいただけます。
就労移行支援を通して就職を目指したい方は、気になる事業所を見学してみるのがおすすめです。
メールによるお問い合わせも随時受け付けています。まずは気軽にお問い合わせください。
※1 参考:アクセスジョブ.「アクセスジョブとは」 (参照2025-04-30)
※2 参考:アクセスジョブ.「トップページ」 (参照2025-04-30)