
就労移行支援と就労継続支援の違いとは? 就労継続支援A型・B型についても解説
公開日:2025.07.11
更新日:2025.12.19
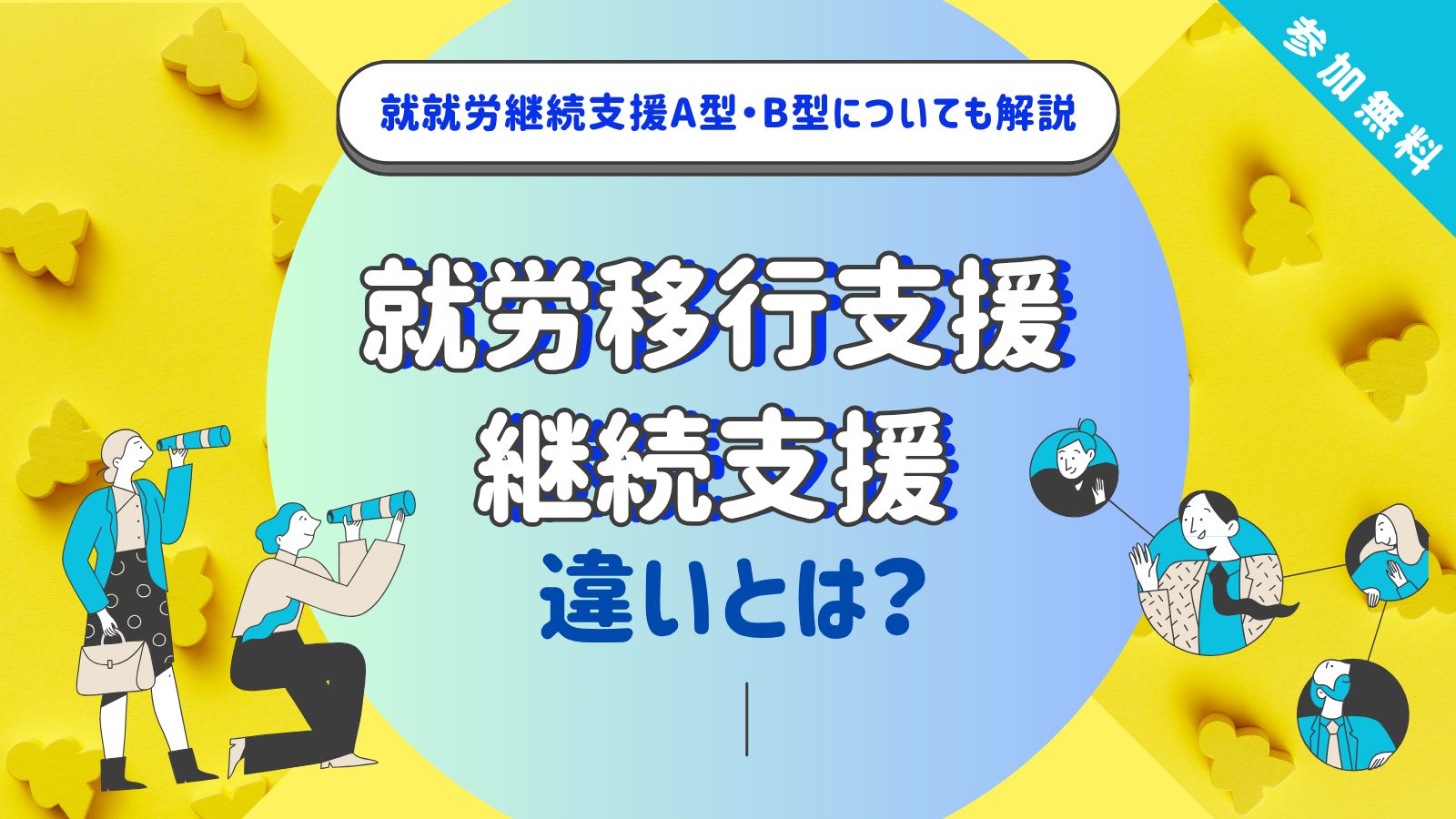
障がいや難病を抱えている方の就労をサポートする障がい福祉サービスとして、「就労移行支援」と「就労継続支援」があります。
本記事では、就労移行支援と就労継続支援の概要や違い、就労継続支援A型・B型の特徴などを解説します。
本記事を参考にして、2つの障がい福祉サービスの違いを理解し、ご自分に適したサービスを利用しましょう。

1.就労移行支援とは?
就労移行支援とは、障がいや難病を抱えている65歳未満の方のうち、一般企業での就職(一般就労)を目指す方を対象とした障がい福祉サービスです(※)。
利用期間は原則2年間で、主に、就労に必要なスキルや知識の習得を目的としています(※)。受けられる支援は、以下の通りです。
- 職業訓練
- 職場体験
- 自立のための生活支援
- 就職活動支援
- 就職後の定着支援
訓練機関のような位置付けで、トレーニングの受講を主な目的としているため、原則としてサービス利用中は給与や工賃は発生しません。ただし、収入を得ることによるやりがいや、金銭管理を身に付ける目的で、独自に工賃を支給している就労移行支援事業所も一部あります。
※参考:厚生労働省.「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」 (参照2014-09-25)
2.就労継続支援とは?
就労継続支援とは、障がいや難病のある方のうち、一般企業への就職(一般就労)が難しい方を対象とした障がい福祉サービスです。

就労継続支援では、就労や生産活動の機会が継続的に提供されます。就労に必要な知識やスキルの習得に向けた訓練なども受けられますが、あくまで就労の場を確保することがメインのサービスです。利用期間に制限はありません。
就労継続支援には就労の対価として、雇用契約を結んで給与が支払われる「A型」と、雇用契約を結ばず工賃が支給される「B型」があります。
3.就労移行支援と就労継続支援の違い
ここでは、就労移行支援と就労継続支援の違いを一覧にまとめました。
| 就労移行支援 | 就労継続支援 | ||
| A型 | B型 | ||
| 目的 | 一般企業への就労に必要な知識・スキルの習得 | 就労・生産活動の機会提供 | 就労・生産活動の機会提供 |
| 対象となる方 | 障がいや難病を抱えている方で、一般就労を希望する方 | 障がいや難病を抱えている方で、一般就労が難しいものの、雇用契約を結んでの就労が可能な方 | 障がいや難病を抱えている方で、一般就労や雇用契約を結んでの就労が難しい方 |
| 年齢制限 | 65歳未満(※1) | 65歳未満(※1) | 制限なし |
| 利用期間 | 2年間(※1) | 制限なし | 制限なし |
| 雇用契約 | なし | あり | なし |
| 給与・工賃 | 基本的になし | 給与あり | 工賃あり |
| 平均収入 | – | 86,752円(※2) | 23,053円(※2) |
就労移行支援は、一般企業での就労に向けたスキル・知識の習得が主な目的です。一方、就労継続支援は就労・生産活動の機会を提供することが主な目的となります。
そのため、就労移行支援は基本的に給与や工賃はありませんが、就労継続支援には給与もしくは工賃が支払われます。また、就労移行支援は利用期間が原則2年間と決まっていますが、就労継続支援は利用期間の制限はありません(※1)。
※1 参考:厚生労働省.「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」 (参照2014-09-25)
※2 参考:厚生労働省.「令和5年度工賃(賃金)の実績について」 (参照2025-05-15)
4.就労継続支援A型について
就労継続支援にはA型とB型があります。
就労継続支援A型は、障がいや難病がある方で、一般企業への就職は難しいものの、雇用契約を結んでの就労ができる65歳未満の方を対象とした障がい福祉サービスです。
具体的には、以下のような方を対象としています(※)。
- 就労移行支援を利用したが、一般就労がかなわなかった方
- 特別支援学校を卒業後、一般就労を目指したものの雇用が実現しなかった方
- 一般企業への就労経験があり、現在離職中の方


就労継続支援A型は、利用者と事業所が雇用契約を結んで就労に臨みます。そのため、報酬として、労働基準法に基づき最低賃金以上の給与を支払われるのが特徴です。以下のような就労機会が提供されます。
- データ入力
- 飲食店のホールスタッフ
- 商品などの梱包
- 清掃
- 配達・宅配の補助
- 自動車部品などの加工
- 農作物の栽培・出荷
就労を通して一般就労が可能な知識やスキルが身に付いた場合は、一般企業への移行支援を受けることも可能です。
※参考:厚生労働省.「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」 (参照2014-09-25)
5.就労継続支援B型について
就労継続支援B型は、障がいや難病を抱えている方で、一般企業での就労や雇用契約を結んでの就労が難しい方を対象とした障がい福祉サービスです。具体的には、以下のような方を対象としています。
- 就労経験はあるが、年齢・体力的に一般就労が難しい方
- 就労移行支援を利用し、就労継続支援B型が適していると判断された方
- 上記に該当しない方で、50歳以上の方、もしくは障害基礎年金1級を受給している方(※)
就労継続支援B型は、A型と異なり雇用契約を結びません。そのため、最低賃金は保障されませんが、体調や障がいの状態に合わせて、労働時間・労働日数を無理なく調整できるのが特徴です。労働の対価として、工賃が支払われます。
提供される就労機会の例は、以下の通りです。
- 部品の加工
- 農作業
- 手工芸
- 飲食店での調理
- 製菓
- 衣類のクリーニング
- 清掃
- 商品などの梱包


就労継続支援B型を利用する方の中には、スキルや体力が付いて、一般就労や就労継続支援A型の利用を目指す場合もいます。
※参考:厚生労働省.「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」 (参照2014-09-25)
6.就労移行支援の利用に向いている方
ここからは、就労移行支援の利用に向いている方の特徴をご紹介します。

●一般企業に就職したい方
就労移行支援の利用に向いているのは、一般企業への就職(一般就労)を目指す方です。
就労移行支援では、職業訓練や就職活動の支援を受けられます。実際に一般企業に足を運び、職業体験をすることも可能です。
将来、一般企業で働きたいと考えているのなら、就労移行支援を利用すると良いでしょう。
一般就労を目標としているものの、今すぐの就職に自信がない方、スキルアップした上で就職を目指したい方、自力での就職がなかなかうまくいっていない方にもおすすめです。
●就労継続支援利用者で、一般就労(一般的な職場への就職)を目指す方
就労継続支援を利用した方で、将来的に一般就労を目指す方も、就労移行支援が向いています。

就労継続支援は就労機会の提供が主ですが、一般就労への移行に向けた支援も行っています。
就労継続支援を利用して、一般就労を目指したいという気持ちが芽生えたなら、就労移行支援への切り替えを検討すると良いでしょう。就労継続支援利用中に、就労移行支援に切り替えることも可能です。
就労移行支援の見学や体験利用をしてみることで、自身の方向性が見えてくるかもしれません。
結果として現状維持となっても気にすることはありません。結果として現状への納得感につながるため、悪いことではないでしょう。
ただし、就労移行支援は知識・スキルの習得を目的としているため、基本的に給与や工賃の支払いはありません。今まで就労継続支援で得られた収入はなくなってしまうため、利用の際は考慮した上で注意が必要です。
7.就労継続支援の利用に向いている方
次に就労継続支援の利用が向いている方の特徴をご紹介します。
●一般就労が不安な方・困難な方
就労継続支援は、働く意欲はあるものの、障がいや病気の特性、体調面の不安などにより、一般就労が不安な方や困難な方に適したサービスです。
就労継続支援は、一般就労が難しい方を対象としたサービスなので負担の少ない業務や柔軟な働き方の中で、継続的な就労の機会を得られます。
就労移行支援を受けたものの、一般就労が難しいと判断された方にも適しているでしょう。
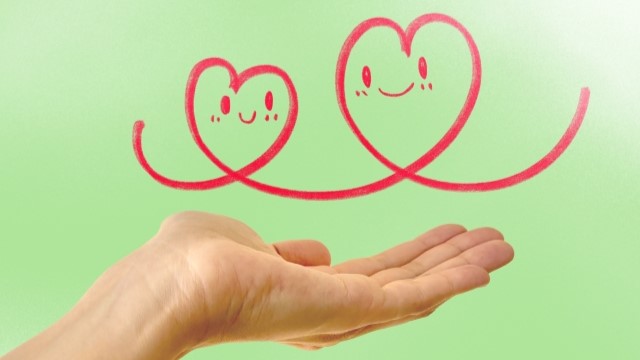
●ご自身の障がい特性に対して適切な配慮を受けながら働きたい方
就労継続支援は、ご自身の障がい特性に対して、適切な配慮を受けながら働きたい方にも適しています。
例えば、一般企業で障がい者雇用として働いていた方でも、年齢や体調によって、従来の働き方が難しくなった方も、支援の対象です。就労継続支援なら、一人ひとりの障がい特性を踏まえた上で、その方に適した就労機会を提供してもらえます。
特に就労継続支援B型は、勤務日数・時間に柔軟なのが特徴です。体調に合わせて作業内容や量を調整しやすいため、自分のペースで無理なく社会との関わりを持ちたい方に適しているでしょう。
8.就労移行支援と就労継続支援、両方利用することはできる?
原則として、就労移行支援と就労継続支援の同時利用はできません。いずれのサービスも日中に行われ、時間帯が重なるからです。

ただし、両方の利用に関して、厚生労働省は明確なルールを定めていません。
利用者の状態や支援の必要性によって、市区町村が特例的に併用を認めた場合は、両方同時に利用できるケースもあります。例えば生活面の支援を受けながら職業訓練を補完的に実施するような状況です。
詳しくは市区町村の障がい福祉窓口などにご相談ください。
一方、就労の状況や希望に応じて、就労移行支援から就労継続支援への切り替えや、その逆への切り替えは可能です。
9.迷ったらまずは見学か問い合わせをしてみる
就労移行支援と就労継続支援のどちらを利用すべきか判断に迷う場合は、まずは事業所に見学できるかどうかを問い合わせてみましょう。
どのような支援が受けられるのか、どのような就労機会を得られるのかを直接知ることで、自分にとって適切なサービスを具体的にイメージしやすくなります。

就労系の障がい福祉サービスは、それぞれの特性や体調に合った支援を受けられることが重要です。少しでも不安や疑問がある場合は、早めに情報収集を行うようにしましょう。
●就労移行支援事業所を見学するまでの流れ
就労移行支援事業所への見学までの一般的な流れを、簡単にご紹介します。
- 就労移行支援事業所のWebサイトにアクセスする
- 「見学申し込みフォーム」を入力して送信する
- 担当者からの連絡を待つ
- 日程を調整する
- 見学の日時が決まったら、当日事業所に行く
- サービス内容や支援の流れの説明を受ける
- 事業所の設備や雰囲気を案内してもらう
- 分からないことを質問する
事業所によって異なる場合もありますが、一般的な流れはこのようになっています。電話での申し込みを受け付けている事業所もあります。
●就労移行支援事業所に問い合わせするまでの流れ
就労移行支援事業所に問い合わせする際の一般的な流れをご紹介します。
- 就労移行支援事業所のWebサイトにアクセスする
- Webサイト上の「お問い合わせ」ボタンをタップする
- 「お問い合わせフォーム」に入力する
- 担当者からの連絡を待つ
- 回答を確認し、必要に応じて対面での相談を申し込む
「いきなり連絡するのは少し不安……」という方は、メールで疑問点や不安な点を質問することも可能です。担当者に質問することで、事業所のイメージがつかみやすくなるので、気軽に問い合わせてみましょう。
10.【まとめ】自分に合った障がい福祉サービスを利用しよう
就労移行支援も就労継続支援も、障がいや難病がある方の働きたい気持ちを支援する障がい福祉サービスです。サービスによって目的や対象としている方が異なるので、自分に合ったサービスを選ぶことが大切です。

どちらを利用するか迷ったら、「どれが正解か」ではなく、「今の自分に合っているか」で選ぶことが大切です。
- すぐに働くことを優先したい
- 働く前に準備や練習をしたい
- 将来の一般就職を視野に入れたい
こうした考え方によって、選ぶ制度は変わります。
一人で判断が難しい場合は、制度の利用を前提としない相談をしてみるのも一つの方法です。
自分に合う就労支援を、整理してみませんか?
就労継続支援A型・B型・就労移行支援には、それぞれ向いているタイミングや目的があります。
「今の自分にはどれが合っているのか」
「このまま進んで大丈夫か」
と迷っている方に向けて、制度の比較や進み方を個別にご説明しています。
お問合せ:就労移行支援アクセスジョブ
アクセスジョブでは、オーダーメイドの個別支援プログラムで、障がいをお持ちの方の「働きたい」を実現します。資格取得プログラムやパソコン操作の基礎学習など、就職に役立つ多彩なカリキュラムを用意しています。

アクセスジョブの就労支援が少しでも気になったというかたは、ぜひ最寄りの事業所をチェックしてみてください。以下の「事業所を探す」からお探しいただけます。
就労移行支援を通して就職を目指したい方は、気になる事業所を見学してみるのがおすすめです。
メールによるお問い合わせも随時受け付けています。まずは気軽にお問い合わせください。
※1 参考:アクセスジョブ.「アクセスジョブとは」 (参照2025-04-30)